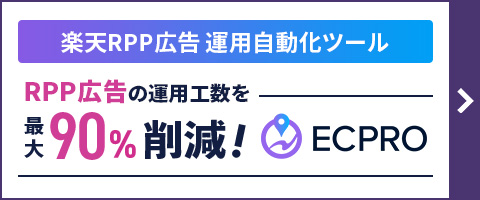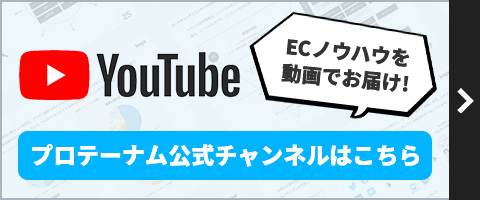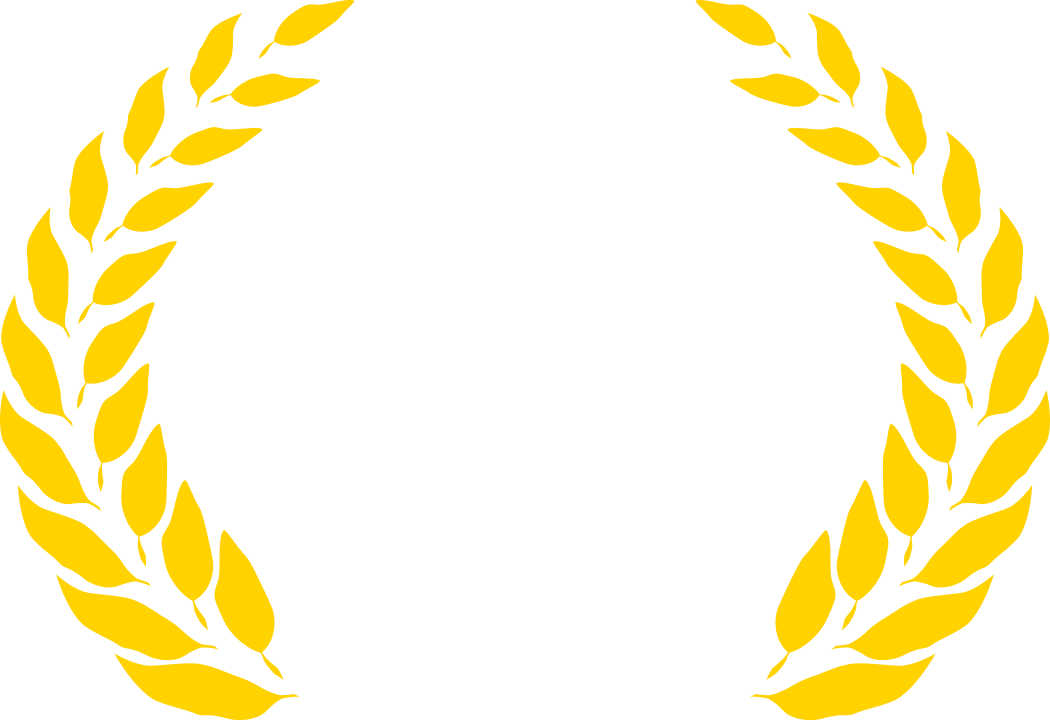ECサイトにおけるKPIとは?最適な目標設定から分析方法まで徹底解説!

本記事を閲覧頂きありがとうございます。 我々はECにおける総合的な売上向上サービスを展開しています。
楽天、Amazon、Yahoo!ショッピングの大手ECモールや自社サイトのご支援実績のもと、EC売上向上のノウハウをお届けします。
Contents
- 1.KPIとは
- 2.ECサイトにおいてKPIを定める重要性
- 3.ECサイトにおけるKPIとKGIの違いとは?
- 4.ECサイトにおいてKPI・KGIを定めるうえで重要なことは?
- 5.ECサイトにおけるKSFとは?
- 6.ECサイトにおける大まかなKPI項目
- 7.ECサイトにおけるマーケティング活動のKPI
- 8.月間指名検索数
- 9.適正在庫を維持するためのKPI
- 10.CVR向上のためKPIツリーを作成しよう
- 11.KPIツリーを設定する方法
- 12.ECサイトにおけるKPIツリーの活用方法
- 13.ECサイトのページへのアクセス数を増やすには?
- 14.ECサイトのページの転換率(CVR)を増やすには?
- 15.ECサイトのページの客単価を増やすには?
- 16.KPI・KGIの目標を達成した後のアクション
- 17.KPIを達成するために必要な確認事項
- 18.ECサイトにおけるKPI設定をする際の具体例
- 19.ECサイトの成長に向けた効果検証
- 20.ECサイトの成長に向けたGoogleアナリティクスの活用方法
- 21.ECサイトにおける仮説を実行した後の分析
- 22.ECサイトにおける成功した事例の紹介
- 23.まとめ
1.KPIとは

KPI=Key Performance Indicator(重要業績評価指標)の略称です。
組織の目標に向けて業績評価の指標を具体的に示したのことをいいます。
2.ECサイトにおいてKPIを定める重要性

ECサイトでの販売を行っていると、実店舗で販売をするよりもデータから得られる情報が多く、目的を定めておかないとどのデータを基に次のアクションに繋げていけばよいのかがわかりにくくなります。
そんな時にKPIを定めておくことで、目的に向けた仮説、検証をスムーズに行うことができ、自分たちの行動が分析しやすくなります。
ECサイトを運営するにあたり、日々PDCAを回し、どのような施策が効果的なのかを日々検証する必要があります。その際にKPIを定めていないと、個人の感情や考えによって施策をやみくもに打つことになってしまいます。
ただし、KPIそのものが重要というわけではありません。 KPIを設定したあとに、その目標に向けて次にどのような施策を打つのかが重要です。
また、KPIを設定する組織で動いて運営をしていく際に、共通認識をもって運営していくことができます。組織間で目標の認識の齟齬がないようにKPIはしっかり設定しましょう。
3.ECサイトにおけるKPIとKGIの違いとは?

KPIに似た言葉で「KGI」というものがあります。
KGI=Key Goal Indicator(重要目標達成指標)
KGIとは、事業における最終目標という意味でつかわれます。そのため、KPIはKGIを達成するための中間目標となる指標になります。
(例)ECサイトで月の売上1,000万円を目指すために、まずは来月、新規顧客を500人獲得したい。
KGI:月の売上1,000万円
KPI:新規顧客を500人獲得
上記のように、KPIとはKGIを達成するための定量的な指標として用いられます。
そのため、KPIを定める際は、長期的な目標を達成するために今できることを出来るだけ分かりやすく設定することが大事です。
4.ECサイトにおいてKPI・KGIを定めるうえで重要なことは?
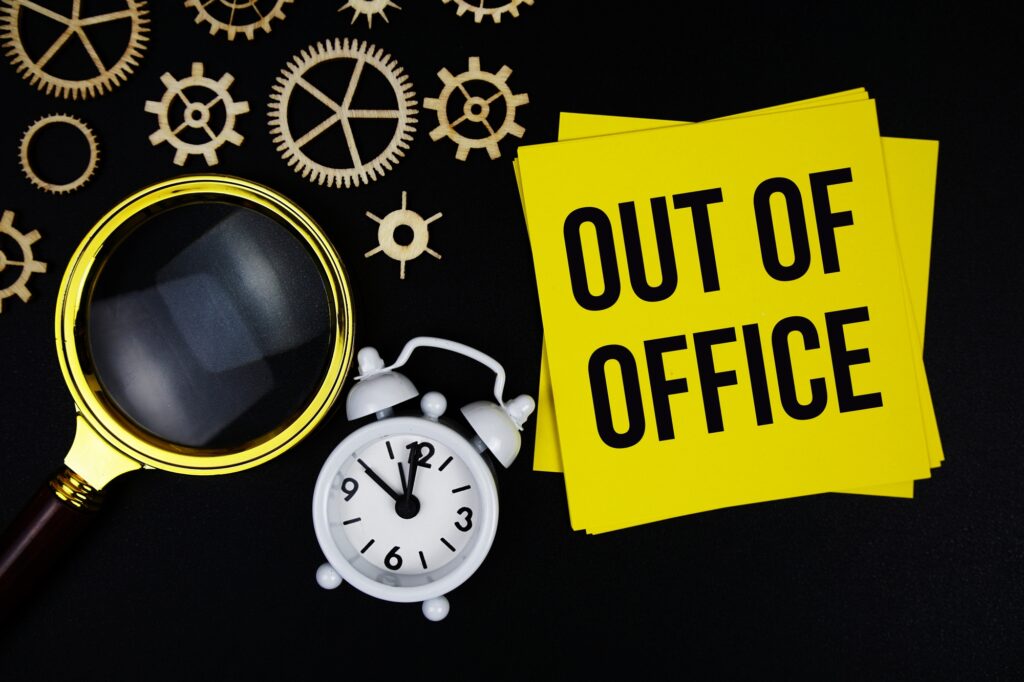
ECサイトでKPI・KGIを設定する上で、特に以下の3つが大切になります。
- KPIとKGIを紐づける
- KPIは定量的に設定する
- KGIは期間設定をする
詳細に解説していきます。
4-1.KPIとKGIを紐づける
KPIもKGIも設定した!という方でも、KPIとKGIが連動していないケースがよく見られます。
KGIで最終目標を定めた場合、KPIはその最終的な目標に沿ったものでなければなりません。
ここで、ECサイトの売上を伸ばすために必要な要素を考えてみましょう。
売上 = アクセス数 × 転換率(CVR) × 客単価
という構成になっています。
ここから考えると、KPIが、アクセス数、転換率(CVR)、客単価であり、KGIが売上です。
設定したKGIに沿ったKPIが定められているかをよく確認しましょう。
4-2.KPIは定量的に設定する
KPIを設定する際は必ず「定量化」して設定しましょう。
数値で目標を定めることで、指標が明確になり、自分たちが目標を達成しているか否かを正確に判断しやすくなります。
KPIとは、KGIを達成するためのプロセスなので、出来るだけ明確に設定することで自分たちが進むべき道のりが分かりやすくなります。
4-3.KGIは期間設定をする
KGIやKPIは、ECサイトにおいて売上や目標、ゴールを設定し、達成するための指標として設定します。そのため、KPIやKGIというのは、あくまで目標を達成するために次に必要なアクションを明確にするための指標です。
そこで重要になるのが、KGIは期間を決めて設定する、ということです。
KGIの期間を決めずに運営を続けると、いつまでたっても目標が達成できず、売上が伸びにくくなるというのはよくある話です。KGIの期間設定をすることで、目標が明瞭になり、次へのアクションをどんどん考えていけるようになります。段取りの悪いECサイト運営にならないように、KGIはしっかりと期間を定めましょう。
5.ECサイトにおけるKSFとは?

KSF=Key Success Factor(重要成功要因)
ECサイトにおけるKSFとは、KGIを実現するためになにが必要であるかを言語化したものになります。
例えば、KGIが「売上〇〇%アップ」だとすると、それを達成するためのKSFには「商品の認知度アップ」「商品の購入単価アップ」といったものが考えられます。
KSFはKGIとして設定した目標に不可欠な要素となるので、こちらもしっかりと検討していく必要があります。
6.ECサイトにおける大まかなKPI項目

ECサイトの主要なKPIは、概ね以下の項目に集約されます。
- アクセス数
- 転換率(CVR)
- 客単価
- 回転率
- リピート率
これらの指標は、サイトのパフォーマンスを把握し、成長を促進するための重要な要素です。
以下より、ECサイトで売上アップを目指すための主要なKPIについて詳細に解説していきます。
①アクセス数
自社のサイトに訪れるユーザー数、つまり「アクセス数」は、ECサイトの成功に欠かせない重要な指標です。具体的には「PV(ページビュー)」「セッション」「UU(ユニークユーザー)」といったデータが該当します。これは、ECサイトに限らず、ほとんどのビジネスに共通することですが、サービスを見てもらうこと自体が非常に大切な指標になってきます。
もしアクセス数が伸び悩んでいる場合は、SEO対策やWEB広告、アフィリエイト、またはモール出店などの施策を取り入れることで、集客を促進することができます。
②転換率(CVR)
ECサイトにおいて、改善後に売上が飛躍的に伸びる可能性が高い指標が「転換率(CVR)」です。例えば、CVRが1%から3%に改善できたと仮定すると、売上は3倍にまで増える可能性があります。つまり、アクセス数が同じでも、転換率を改善するだけで、売上の大きな伸びを見込むことができるのです。
多くのECサイトの運営者が、CVRを向上させるために日々様々な取り組みを行っています。例えば、ボタンの色を目立つものに変えたり、購入までの導線をスムーズに見直したり、特典や割引のオファーを目立たせる、といったものです。あるECサイトでは、カートに商品を入れた後に「あと○○円で送料無料!」と表示することで、購入意欲を高める施策が実施されているケースもあります。このように、小さな改善が積み重なることで、CVRは大きく変化する可能性があります。
③客単価
客単価の向上は、ECサイト運営における重要なテーマの一つです。
そのための施策としては、関連商品を提案して同時購入を促したり、一定金額以上の購入で送料無料にするなどの工夫が挙げられます。
また、顧客一人当たりの購入金額を高めるアプローチとは別に、近年注目を集めているのが「サブスクリプションモデル」の導入です。定期的な購入を促すことで、安定した収益を見込めます。
さらに、現代のECビジネスにおいては、一回の購入金額だけでなく、「ライフタイムバリュー(LTV)」という視点を持つことが不可欠です。LTVとは、一人の顧客が生涯にわたって自社にもたらす収益の総額を示す指標です。
短期的な客単価の向上策と並行して、顧客との長期的な関係性を構築し、LTVを高める戦略を検討することをおすすめします。
④回遊率
回遊率とは、ECサイトを訪れたユーザーが、サイト内の様々なページをどれほど閲覧したかを示す指標です。
例えば、あるECサイトの1日のアクセス数が1,000件あったとします。しかし、多くのユーザーがトップページを見ただけで離脱してしまい、商品詳細ページや他のカテゴリページ、ブログコンテンツなどをほとんど見ていない場合、回遊率は低いと言えます。これは、顧客が目的の商品を見つけられなかったり、サイトの情報に魅力を感じなかったりする可能性を示唆しています。
たとえサイトへのアクセス数が多かったとしても、このように回遊率が低い場合は、顧客が十分に満足していない可能性が考えられます。
そのため、ECサイトの品質向上を図る上で、回遊率を重要なKPIとして設定し、その推移を注視することが不可欠です。もし回遊率が低下傾向にあれば、サイトのデザインや導線、コンテンツの見直しなどの対策を検討する必要があります。
逆に、回遊率の数値が高まるほど、顧客は多くの商品や情報に触れ、サイトへの興味や理解を深めていると考えられます。これは、購買意欲の向上や顧客満足度の向上に繋がる可能性が高くなります。ぜひ、回遊率をKPI項目の一つとして定め、データに基づいたECサイトの改善を進め、成長にお役立てください。
④リピート率
ECサイトにおける持続的な成長の鍵となるのが、リピート率です。これは、一度商品を購入してくださったお客様が、再び別の商品などを購入してくれる割合を示します。新規顧客の獲得だけでは限界があるECの世界において、既存顧客に繰り返し選んでいただくことは、ビジネスの安定と発展に不可欠と言えるでしょう。
リピート率をKPIとして捉え、その向上を目指す上で、特に注力したいのは以下の4つの要素です。
- SNSでのエンゲージメント: 魅力的なコンテンツを通じて顧客との繋がりを深め、再訪・再購入を促します。
- 会員制度の導入: 特別な特典や体験を提供することで、顧客のロイヤリティを高め、継続的な利用を促進します。
- キャンペーンの実施: 定期的なキャンペーンやイベントは、購入意欲を刺激し、再購入のきっかけを生み出します。
- 快適なサイトデザイン: 洗練されたデザインと使いやすいインターフェースは、顧客満足度を高め、再訪意欲へと繋がります。
これらのKPI設定を実践し、顧客との良好な関係性を育みながら、リピート率の着実な向上を目指しましょう。
⑤離脱率
カート離脱率とは、ECサイトを訪れた顧客が商品をカートに入れたにも関わらず、購入手続きを完了せずにサイトを離れてしまう割合を示すものです。「カゴ落ち率」とも呼ばれます。
株式会社イー・エージェンシーの調査によると、日本のECサイトにおけるカート離脱率は平均で約68.2%という結果が出ています。これは、実に約7割もの顧客が購入に至っていないということを意味し、この数値を改善するだけで売上向上に大きく貢献する可能性があります。
カートから離脱してしまう理由は多岐にわたりますが、主な要因としては、予期せぬ費用の発生(送料や追加料金など) や 商品が手元に届くまでの時間 などが挙げられます。
ECサイトのカート離脱率を詳細に分析し、配送業者の再検討や送料体系の見直しといった対策を講じることで、改善を図りましょう。
⑥顧客獲得単価
顧客獲得単価とは、一人の新しい顧客を獲得するために投じた、あらゆるマーケティング施策の総コストを、獲得した顧客数で割って算出される指標です。英語ではCustomer Acquisition Costと表記され、「CAC(シーエーシー)」と略されます。
類似の指標として「CPA(Cost Per Acquisition)」がありますが、こちらも顧客獲得単価と訳されます。CACが全体のマーケティングコストを対象とするのに対し、CPAは個々のマーケティング施策にかかったコストと、そこから獲得できた顧客数に基づいて算出されます。全体像を把握するならCAC、個々の施策の効果を分析するならCPA、と考えると理解しやすいでしょう。
ECサイトの運営初期段階ではCACを注視し、事業規模が拡大してきた段階では、CPAを用いて各マーケティング施策の費用対効果を詳細に評価していくのがおすすめです。
⑦売上高
売上高とは、特定の期間内に生み出された収益の総額を示すものです。ECサイトの規模を測る上で不可欠であり、「顧客単価」「訪問者数」「CVR」といった重要な要素に分解でき、それぞれをKPIとして管理することができます。
売上高を計測する期間は、1時間、1日といった短いスパンから、1週間、1ヶ月、四半期、1年といったより長い期間まで、ビジネスの特性や管理の目的に応じて柔軟に設定できます。これはECサイトに限らず、あらゆるビジネスにおいて、週間、月間、年間といった単位で定期的に観測することが重要です。
ただし、売上高が増加したとしても、それ以上に経費がかさんでしまっては、利益は減少してしまいます。「人件費」「広告運用費」「サイト維持費」といった各種経費に関するKPI設定も、決して忘れてはなりません。
⑧LTV
LTVはLife Time Valueの略であり、日本語では顧客生涯価値と称されます。これは、一人の顧客があなたのECサイトに対して、生涯にわたってどれだけの金額を費やしてくれるかを示すものです。
その計算式は、一般的に「平均顧客単価 × 収益率 × 購買頻度 × 継続期間 − (新規顧客獲得コスト + 既存顧客維持コスト)」で求められます。LTVは単独で算出することも可能ですが、CPA(顧客獲得単価)と比較することで、より具体的で深みのあるKPI設定が可能になります。
すでに述べたように、客単価は短期的な売上を把握する上で有効ですが、中長期的な視点で売上を予測する際には、LTVを含めた検討が不可欠です。例えば、一回の購入金額がそれほど高くなくても、LTVの高い熱心なファンを育成できれば、将来的な集客コストの削減や、安定した収益基盤の構築に繋がるでしょう。
7.ECサイトにおけるマーケティング活動のKPI

マーケティング活動におけるKPIは、SEO(検索エンジン最適化)やEFO(エントリーフォーム最適化)といった改善施策、そして広告や各種マーケティング目標の達成度合いを把握するための重要な指標群です。
これらは、売上や利益といったビジネスの根幹を支える取り組みの進捗を測る上で、決して見過ごすことのできない存在です。なぜなら、マーケティングにおけるKPIの数値は、最終的な売上や利益のKPIにも直接的な影響を与えるからです。
さらに、これらの指標を詳細に分析することで、どの顧客がどのような商品を購入したのかといった貴重な情報を把握できます。これは、今後のより効果的なマーケティング施策の立案や、顧客ニーズに基づいた商品開発に大いに役立ちます。
ここからは、ビジネスの成長を力強く推進するためのマーケティングに関するKPIについて、さらに深く掘り下げて解説していきます。
①滞在時間
滞在時間とは、顧客があなたのECサイトにアクセスしてから離脱するまでの時間を指します。
短時間での購入は効率的な顧客行動と言えますが、滞在時間の長短だけでECサイトの品質を断定することはできません。なぜなら、目的の商品をすぐに見つけて購入する顧客が多い場合、滞在時間は短くなる傾向があるからです。
しかしながら、極端に短い滞在時間が多い場合は、顧客が求める商品とサイトの品揃えや情報との間にミスマッチが生じている可能性が考えられます。
一方、滞在時間が長い場合は、顧客がサイト内の情報をじっくりと閲覧し、快適な時間を過ごしている可能性が高まります。これは、商品の発見や比較検討を促し、結果として販売機会の増加やリピート率の向上に繋がる可能性があります。
②トラフィックソース
トラフィックソースとは、顧客があなたのECサイトへどのようにしてたどり着いたのか、その流入経路を示すものです。
具体的には、広告、オーガニック検索、SNS、メールマガジンなど、多様なチャネルを通じて顧客がサイトを訪れる状況を把握することができます。
この情報を活用することで、例えばSEO(検索エンジン最適化)に注力しているのであればオーガニック検索からの流入数増加をKPIに設定したり、SNS運用に力を入れているのであればSNS経由の流入数増加をKPIに設定したりといった、具体的な戦略に繋げることが可能です。
トラフィックソースを分析することで、あなたのECサイト全体、あるいは個々のページに対して、どのチャネルが最も効果的に顧客の訪問を促しているのかについての貴重な洞察が得られます。
③メルマガ購読者数
メルマガ購読者数とは、あなたのECサイトのメールマガジンに登録している顧客の総数を指します。
この購読者数は、広告費用などをかけずに直接アプローチできる可能性のある見込み顧客の規模を示すものと捉えられます。したがって、購読者数が多いほど、より多くの顧客に対して情報を発信し、関係性を構築する機会が増加します。
さらに、購読者のデモグラフィックデータや登録経路などの関連情報を分析することで、ターゲットとする顧客層への訴求が適切に行えているかを確認することができます。
クーポンやキャンペーン情報といった魅力的なコンテンツを定期的に配信することで、メルマガ購読者数の増加を促進し、顧客とのエンゲージメントを深めていきましょう。
④メール開封率
メール開封率とは、ECサイトから送信されたメールが、受信者の受信箱で実際に開封された割合を示す重要な指標です。この数値が低い場合、顧客に情報が届いていない可能性を示唆しており、放置すればマーケティングの効果を大きく損なうことになります。
開封率を改善するためには、まず顧客の興味を引く魅力的なタイトルを考案することが不可欠です。また、長期間にわたり反応のない非アクティブ顧客や、メールへの関与が極めて低いエンゲージメントの低い顧客を配信リストから見直すことも有効な手段となります。
メール開封率をKPIとして設定し、効果的なメールマーケティングを展開するためのポイントは以下の通りです。
- 明確な目標設定: 何のためにメールを配信するのか(例:特定商品の販売促進、ブランド認知度向上、顧客ロイヤリティ強化など)、その目的を明確にし、達成すべき具体的な目標開封率を設定します。
- ベンチマークとの比較: 同業他社の平均開封率を参考にしつつ、自社の顧客層や配信内容、過去のデータを考慮して、現実的かつ挑戦的な目標値を設定します。
- データに基づいた目標策定: 過去のメール配信実績を分析し、曜日、時間帯、タイトルなどの要素と開封率の関連性を把握した上で、より精度の高い目標を設定します。
- 達成可能な範囲での目標設定: 非現実的な高すぎる目標は、チームのモチベーション低下を招き、焦りから不適切な施策を実行してしまう可能性があります。
- 継続的な分析と改善: 市場の動向や顧客のニーズは常に変化します。定期的に開封率の推移を分析し、目標の見直しや配信戦略の修正を行うことで、常に最適な状態を維持します。
⑤メールクリック数
前述のメール開封率は、顧客がメールの封を開いたか否かを示すものですが、クリック率は、そのメール本文中に設置されたリンクが実際にクリックされた割合を指し示す、よりアクションに直結する指標です。
なぜなら、魅力的なコンテンツが書かれたメールであっても、リンクがクリックされなければ、ECサイトへの誘導、ひいてはトラフィックの増加や売上への貢献は期待できないからです。そのため、一般的に、メールマーケティングにおいては開封率よりもクリック率の方が、より本質的な成果を測る上で重要なKPIと捉えられています。
もし、メールの開封率が高いにも関わらず、ウェブサイトへの流入数増加や売上向上といった具体的な成果が見られない場合、その原因はメール本文内のリンクが顧客の興味を引けていない、つまりクリック率の低さにある可能性が高いと考えられます。
8.月間指名検索数
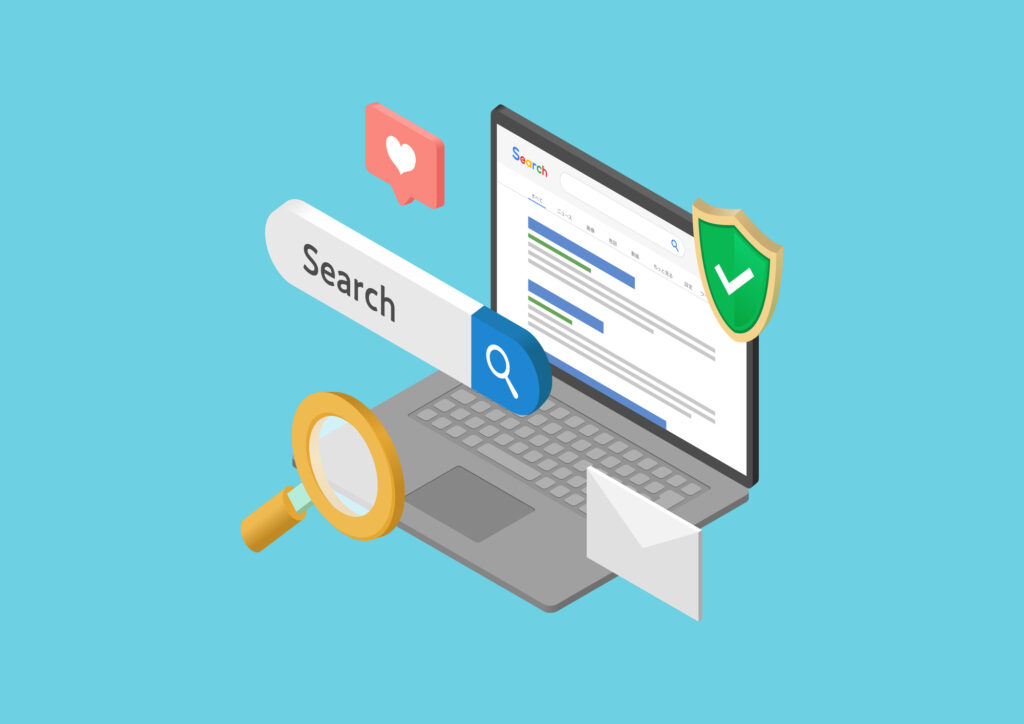
月間指名検索数とは、特定の1ヶ月間において、あなたのECサイトのブランド名やサイト名が検索エンジンでどれほど検索されたかを数値化したものです。特に運営を開始したばかりのECサイトにとって、顧客への認知度向上は最優先に取り組むべき課題の一つであり、この指名検索数はその進捗を測る上で非常に適切なKPIとなります。
指名検索数の把握には、Google Search Consoleを利用するのが一般的です。その他にも、キーワードプランナーをはじめとする無料・有料のツールが存在しますので、自社のニーズや予算に合わせて最適なものを選択すると良いでしょう。
もし指名検索数が伸び悩んでいる場合、それは現在展開している認知拡大施策が期待する効果を発揮できていないという警鐘です。この結果を踏まえ、Web広告の見直しはもちろんのこと、現代においては不可欠なSNSを活用した集客方法など、多様な施策を検討し、改善を図っていくことが重要となります。
9.適正在庫を維持するためのKPI

ECサイト運営において、適正在庫の維持は事業の成否を左右する極めて重要な要素です。在庫不足は販売機会の逸失を招き、過剰な在庫は保管コストの増大に直結するため、繊細なバランス感覚が求められます。
この均衡を保ち、常に理想的な在庫状態を追求するためには、「最適在庫を測る指標(在庫管理に関するKPI)」を設定し、定期的なモニタリングを通じて状況を把握し、継続的に必要な対策を講じることが不可欠です。
ここからは、ECビジネスの生命線を最適化するための鍵となる「最適在庫を測る指標」について、詳しく解説していきます。
①過剰在庫
過剰在庫とは、現在の販売予測や需要に対して、どれほどの在庫が余剰となっているかを示す指標です。この指標を精緻に分析することで、全体の在庫状況はもとより、個々の商品における在庫の余剰量、在庫が倉庫に保管されている期間の長さ、そして商品の売れ行きの速度といった多角的な情報を把握することが可能となります。
過剰在庫の状況を評価する際には、単に在庫の数量だけに着目するのではなく、その在庫が保持されている期間や、在庫の回転率といった動的な側面にも注意を払う必要があります。
特に、長期間にわたり販売に至らず滞留している商品や、市場における需要の変化により回転率が著しく低下している商品に対しては、速やかに発注量や発注頻度の見直しを実施することが求められます。
②在庫欠品率
在庫欠品率は、お客様がECサイトで商品を購入しようとした際に、在庫切れで購入できなかったケースが、全体の注文に対してどのくらいの割合で発生したかを示すものです。例えば、100件の注文があったうち、5件で在庫切れが発生し、お客様にご迷惑をおかけした場合、在庫欠品率は5%となります。
具体的に、在庫欠品率が高いと以下のような問題が生じます。
- 販売機会の損失: 本来であれば売れていたはずの商品が売れず、直接的な売上ダウンにつながります。
- 顧客満足度の低下: 「欲しい時に買えない」という経験は、お客様の不満を高め、リピート購入の可能性を下げてしまいます。特に、楽しみにしていた商品が欠品していた場合、お客様は競合他社に流れてしまう可能性が高まります。
- 信頼性の低下: 在庫切れが頻繁に発生するECサイトは、「品切れが多いお店」という印象を与え、お客様からの信頼を失いかねません。「このお店は本当に商品が揃っているのだろうか?」という疑念を抱かせてしまう可能性があります。
在庫欠品率を下げるためには、以下のような具体的な対策が考えられます。
- 需要予測の精度向上: 過去の販売データやトレンドを分析し、より正確な需要予測を行うことで、適切な量の在庫を確保します。AIを活用した需要予測ツールなども有効です。
- 発注サイクルの最適化: リードタイム(発注から納品までの期間)を考慮し、適切なタイミングで発注を行うように発注サイクルを見直します。
- 安全在庫の設定: 予期せぬ需要の増加や納期の遅延に備え、適切な量の安全在庫を設定します。ただし、過剰な安全在庫は保管コストを増やすため、慎重な検討が必要です。
- アラート機能の活用: 在庫数が一定のラインを下回った際に自動的に通知が来るアラート機能を設定し、タイムリーな補充を可能にします。
在庫欠品率と過剰在庫のバランスを取りながら、上記の具体的な対策を実行していくことが、機会損失を最小限に抑え、お客様に快適な購買体験を提供するために重要となります。
③在庫保管コスト
在庫保管コストとは、商品がお客様の手に渡るまでの間、倉庫などの場所で保管するために必要となる様々な経費を指します。これには、保管スペースの賃料や管理費用、商品の品質を維持するための光熱費、そして倉庫から出荷拠点までの輸送にかかる費用などが含まれ、これらの平均的なコストを算出することで求められます。
在庫保管コストを抑制するためには、いかに無駄な在庫を持たず、効率的な在庫運営を行うかが重要となります。つまり、在庫保有率を適正に保ち、平均的な在庫コストを低く抑えることが鍵となります。
そのための具体的な改善策としては、以下のようなものが挙げられます。
- 在庫回転率の向上: 商品が倉庫から出ていくスピードを高めることで、倉庫に留まる期間を短縮し、結果として平均在庫額を低減します。
- 保管スペースの最適化: 需要予測に基づいた適切な在庫量を維持し、不要な在庫を削減するとともに、倉庫内のレイアウトを見直すなどして保管スペースを最大限に効率化することで、保管費用を抑えます。
- 物流業務のアウトソーシング: 自社で倉庫を保有・管理するのではなく、専門の外部業者に倉庫管理業務を委託することで、固定費を変動費化し、コスト削減を図ります。
- 在庫管理システムの導入: リアルタイムでの在庫状況の可視化、入出庫管理の自動化、需要予測のサポートなど、高度な機能を持つ在庫管理システムを導入することで、人的ミスを減らし、より効率的で精度の高い在庫管理を実現します。
これらの対策を組み合わせることで、在庫保管コストを最適化し、ECサイトの収益性向上に貢献することが期待できます。
10.CVR向上のためKPIツリーを作成しよう

ここからは、CVRを最適化させる上で欠かせないKPIツリーについて解説していきます。
10-1.KPIツリーとは
KPIツリーとは、重要業績評価指標(KPI)を、最終的な経営目標である重要目標達成指標(KGI)を頂点として、樹木のように枝分かれさせながら構造的に図式化したものです。
多くのECサイト運営者が、売上をKPIの中心に据えると思いますが、単にKPIの進捗状況を追いかけるだけでは、もし目標未達の場合に、具体的にどのような施策を講じるべきか、その道筋を見出すのは容易ではありません。
しかし、KPIツリーを作成することで、KGI達成のために踏むべきステップが視覚的に整理され、ボトルネックとなっている部分の分析や、改善に向けた具体的なアクションプランの策定が格段に容易になるのです。
10-2.KPIツリーを作成するメリット
「KPIツリー」という言葉は、まだ多くの企業にとって馴染みが薄いかもしれません。そのため、その有効性を理解し、実際に作成できている企業は決して多くないのが現状です。
しかし、KPIツリーを導入することで、これまで以上に事業を飛躍的に成長させる潜在的な可能性が開花するかもしれません。
そこで、KPIツリーを作成することによる3つの重要なメリットをご紹介しましょう。
①課題の発見が容易になる
第一に、KPIツリーによって、KPIが伸び悩んだ際に、その原因や課題を特定しやすくなります。
例えば、売上金額という最終目標(KGI)に対して、転換率(CVR)が目標に届いていない場合を考えてみましょう。そんな時にKPIツリーがあれば、このCVRの下に位置するステップの数値を上から順番に検証していくことで、どの段階で問題が発生しているのかを明確にすることができます。
つまり、KGIという結果から逆方向に分析することで、何が根本的な原因となっているのかを見つけ出すことができるのです。ECサイトにおいては、CVRを改善することができれば、売上を大きく向上させる可能性があります。
事業を成長させていくためには、このように原因を特定し、対策を講じることは不可欠です。しかし、KPIツリーのようにKPIを構造的に可視化していなければ、原因の特定は困難を伴います。
一方、KPIツリーを作成していれば、KGIから順に下のステップへと論理的に検証を進めることができます。CVRを最適化できるかどうかは、KPIツリーを作成し、活用できるかどうかに大きく左右されると言えるでしょう。
②チーム内での情報共有の活発化
第二に、KPIツリーは、チーム内の情報共有を促進する潤滑油となります。
多くの企業で、部門やチームごとに目標が設定され、全体像が見えにくいという課題が存在します。特に、最終目標であるKGIが抽象的である場合、個々の担当者は「自分たちの仕事がどのようにKGI達成に貢献するのか」をイメージしづらいことがあります。
しかし、KPIツリーは、この課題を解決する鍵となります。なぜなら、KGIを頂点に、それを達成するために必要な具体的なKPIが各チームや担当者に紐づけられるからです。
例えば、ECサイトの売上向上というKGIに対し、サイト管理担当者には「バグ発生率の低減」、マーケティング担当者には「新規顧客獲得数」、物流担当者には「配送遅延率の削減」といった、それぞれの業務に直結したKPIが明確に割り振られます。
このように、KPIツリーによって各チームの役割と責任範囲が可視化されることで、「自分たちの仕事はKGI達成のどの部分を担っているのか」が明確になり、組織全体としての共通認識が醸成されます。
その結果、目標達成に必要な情報が、誰のところに、どのような形で存在しているのかが把握しやすくなります。これまで部門間で分断されがちだった情報が、KPIツリーという共通のフレームワークを通じて円滑に共有されるようになり、組織全体の連携と情報共有が活性化するのです。
③課題への対策を迅速に行える
第三に、KPIツリーは、戦略を迅速な実行へと繋ぐ架け橋となります。
ここで言う施策とは、設定されたKPIに基づいて具体的に起こす行動のことです。例えば、「売上を向上させる」というKGIに対し、「顧客数が少ない」という課題がKPIツリーによって明らかになった場合、その具体的な施策として「営業活動を強化する」といったアクションが考えられます。
前述の通り、KPIツリーは、KGI達成を阻む課題の所在を明確にし、その課題がどのチームや担当者の責任範囲にあるのかを特定する上で大きな力を発揮します。
課題が特定され、担当者が明確になっている状態であれば、次に取るべき具体的な施策の検討から実行までのプロセスが、格段にスムーズになります。KPIツリーは、課題発見から対策実行までの時間を大幅に短縮し、変化の激しいビジネス環境において、迅速な対応を可能にするのです。
11.KPIツリーを設定する方法

ここからは、実際にKPIツリーを設定する方法について説明していきます。
11-1.KGIに到達するための仮説を立てる
KPIツリーの構築にあたっては、まずKGI達成のための仮説を立てる必要があります。
KPIツリーの正解は一つではありません。
例えば、売上金額をKGIと設定した場合、KPIとして「商品購入者数」と「一人あたりの平均購入金額」という組み合わせで捉えることもできますし、「新規購入者からの売上金額合計」と「リピーターからの売上金額合計」という異なる視点から分解することも可能です。いずれの分解も、それぞれの事業にとって適切な解釈であり、絶対的な正解というものはありません。
また、一度作成したKPIツリーに基づき事業を運営していく中で、どの数値がKGIに大きな影響を与えているのか、その重要度が見えてくると思います。その段階に至りましたら、作成したKPIツリーに改めて向き合い、設定したKPIが必要であるか、あるいは見直すべき点はないかを検討することが重要です。
つまり、KPIツリーは、まず仮説を立てて構築されるべきものであり、その後も、事業の進捗に合わせて定期的に見直し、改善を重ねていく必要のある、動的な戦略であると言えるでしょう。
11-2.単位を統一する
次に、KPIツリーを作成する上で重要な要素として、単位の統一が挙げられます。
KPIツリーは、最終目標であるKGIを数値で管理し、そこに至るまでのステップを定量的に把握するためのものです。
つまり、KPIツリーの各要素を掛け合わせるなどして計算した結果が、最終的にKGIの単位と一致している必要があります。
もし、KPIの単位が統一されていない場合、計算が正しく行われず、目標達成への道筋を正確に把握することが難しくなる恐れがあります。
したがって、KPIツリーを作成する際には、各KPIの単位を意識的に統一することが不可欠です。単位を揃えることで、数値の
11-3.KPIの設定
次に、KPIの設定についてご説明します。
KGIとして売上金額を設定した場合、KPIの例としては、購入者数などが挙げられます。ただし、KPIを設定する上で、注意すべき点がございます。それは、KPIとなり得る指標を選ぶということです。
KPIとなり得る指標とは、具体的に数値を設定できる指標を指します。例えば、購入者数は明確に数値を設定できますが、「サイトの見やすさ」などは、定量的な評価が難しく、KPIとして設定することは適切ではありません。
KPIツリーを作成する際には、先述の単位の統一と併せて、このKPIの設定に関しても十分にご注意ください。
11-4.「SMART」を意識してKPIの設定を行う
ECサイトにおいてKPIを設定する上で、SMARTというフレームワークを意識することが重要です。
SMARTとは、以下の5つの単語の頭文字を組み合わせたものです。
- Specific:具体的
- Measurable:計測可能
- Achievable:達成可能
- Relevant:関連した
- Time-bound:期限を定めた
以下、それぞれの要素について詳しく解説いたします。
Specific(具体的)
KPIは、誰が見ても解釈が分かれることのないよう、具体的な目標として設定することが重要です。
目標が曖昧な状態では、その達成度を正確に評価することが困難になります。具体的な行動や成果に焦点を当てることが求められます。
例えば、「購入率を大きく上げる」というKPIは、担当者によって解釈が異なる可能性があります。そのため、「購入率を前期の2%から5%に引き上げる」といった形で、数値を明確に設定することが重要となります。
Measurable(計測可能)
KPIは、数値や定量的な指標を用いて測定できる必要があります。
目標の進捗状況や達成度を定量的に評価できるように設定されるべきです。測定可能な目標を設定することで、目標達成に向けた進行状況を正確に把握し、改善のための具体的なアクションを起こすことが可能になります。
KPI設定後は、その達成状況を継続的に追跡していくため、計測可能な指標を選択することが重要です。
Achievable(達成可能)
KPIは、達成可能かどうかを慎重に検討した上で設定することが重要です。
KPIは、現実的かつ達成可能な目標として設定される必要があります。
壮大な目標を掲げることも重要ですが、「売上高を1年で50倍にする」といった非現実的な目標は、達成が困難であると判断され、関係者のモチベーション低下や達成意欲の喪失を招く可能性があります。
適切な資源や能力を用意し、目標達成に向けて必要なリソースを適切に配分することが重要となります。
Relevant(最終目的と関連した指標)
KPIは、組織全体の目標や戦略と密接に関連している必要があります。
設定する目標が、組織のビジョンや方針と合致し、組織全体の成果に貢献するように設定されるべきです。
KPIは、最終目標とも言えるKGI達成への重要な指標となります。そのため、KGIとの関連性を持たせることも重要です。
例えば、KGIが「売上1,000万円」である場合、KPIを「広告費の削減」と設定することは、適切な目標設定とは言えません。
関連性のある目標を設定することで、組織の成果を促進し、意義のある結果を生み出すことが可能になります。
Time-bound(期限が明確)
KPIには、明確な期限や時間枠を設定することも重要です。
目標達成までの期限を明確にすることで、スケジュール管理が容易になり、目標達成に向けた関係者の意識統一や集中の度合いが高まります。
時間枠を設定することで、目標の進捗状況を定期的に確認し、計画を実行するためのスケジュールを立てることが可能になります。
SMARTというアクロニムは、KPIの設定や目標管理を行う上で非常に有効な枠組みであり、目標の明確化や達成度の客観的な評価に大きく貢献します。
11-5.データの分析
データ分析を有効に活用することが、KPIツリー作成の効率化に繋がります。
ECサイト運営においては、KPIとなり得る指標が数多く存在します。そこで、Google Analyticsなどのデータ分析ツールを参考に、主要な要素を事前に洗い出しておくことが重要です。
そうすることで、KPIツリー作成時に、どのKPIを設定すべきか迷うことなく、スムーズに設定作業を進めることができます。
11-6.ユーザーシナリオの作成
Web戦略を策定する際には、ユーザーシナリオを作成することが有効です。
ユーザーシナリオとは、ターゲットとするユーザーが、あなたのWebサイトをどのように利用するのか、そのWebサイトを訪れる目的、そしてその目的を達成し、ニーズが満たされるまでのプロセスを可視化したものです。
このユーザーシナリオを作成することで、Webサイト上でどのような施策を実施する必要があるのか、具体的な方針が見えてきます。
12.ECサイトにおけるKPIツリーの活用方法

KPIツリーとは、事業の目標達成において特に重要となる数値を指します。そして、ECサイトを構成する要素にKPIを分解し、それをツリー状の図で表現したものが、KPIツリーです。
ECサイトの場合、最終目標であるKGIを「売上」とした場合、その達成に貢献するKPIとして、アクセス数、転換率(CVR)、平均客単価(AOV)などを設定することが一般的です。
KPIツリーを作成することで、各要素の進捗状況や、目標達成を阻害している課題点を明確に把握することができます。
13.ECサイトのページへのアクセス数を増やすには?

ECサイトへのアクセス数を増加させることは、事業の成長において非常に重要な要素です。そのための具体的な手法としては、以下のようなものが挙げられます。
- SEO(検索エンジン最適化)を強化し、サイトへの流入を促進する
- コンテンツの量を増やし、新規顧客の獲得を図る
- SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)を積極的に活用し、新規顧客を増やす
- Web広告を導入する
上記の施策を参考に、ECサイトへのアクセス数向上を目指しましょう。
また、新規顧客の獲得と並行して、既存顧客からのリピーターを育成することも、事業の持続的な成長には不可欠です。
その具体的な施策としては、以下のようなものが考えられます。
- 公式LINEアカウントやメールマガジンを活用した情報発信
- 会員ランク制度の導入
- ポイント制度の導入
- 割引クーポンの発行
- 消耗品などにおける定期購入制度の導入
ECサイトへのアクセス数を増やし、かつリピーターを育成するためには、リピーターにとって有益で魅力的な制度の構築を検討することが重要です。
14.ECサイトのページの転換率(CVR)を増やすには?
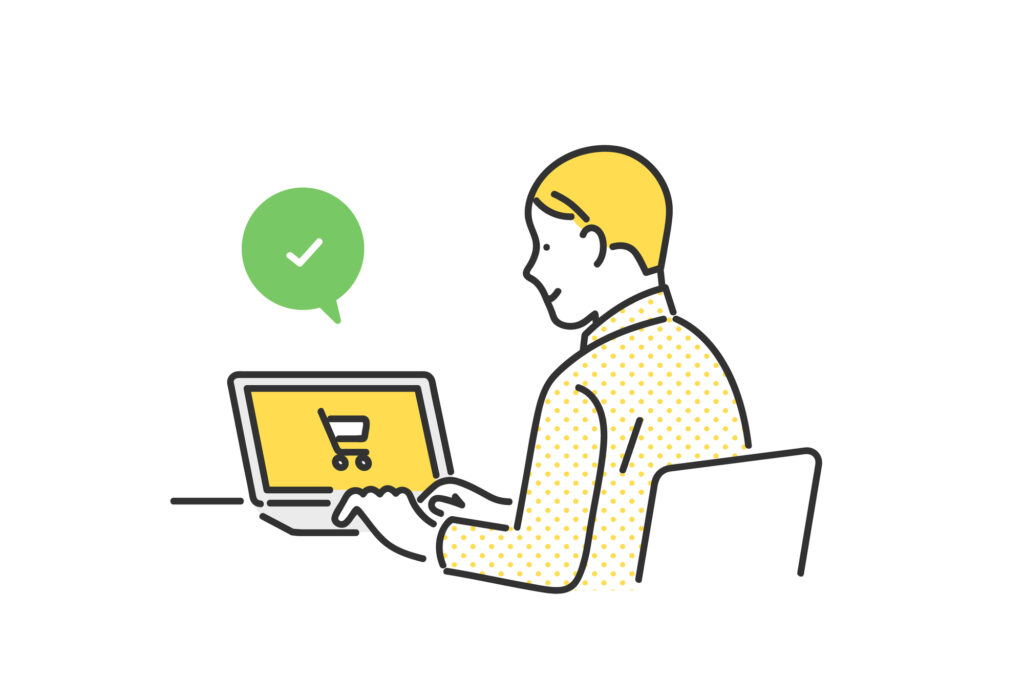
ECサイトにおける商品購入率、すなわちCVR(コンバージョン率)が向上しない場合、その背景には必ず何らかの原因が存在します。重要なのは、その原因を特定し、分析していくことです。
まず、商品購入に至るまでの導線が、顧客にとってスムーズで分かりやすいものであるかを確認することが不可欠となります。
一般的な購入導線としては、以下の流れが挙げられます。
- TOPページ
- 商品一覧
- 商品詳細
- カート
ただし、商品詳細ページの情報が、一部の顧客にとってストレス要因となる可能性も否定できません。そのため、商品詳細ページへの導線を別の経路(例:詳細ボタン)に分離し、購入導線から一旦外すという工夫も、有効な手段となり得ます。
また、商品一覧ページを省略し、商品詳細ページへ直接誘導するという方法も考えられます。
キャンペーン商品、期間限定商品、売れ筋商品などを特別枠で強調表示し、そこから商品詳細ページへ直接遷移させるという手法も、効果的な選択肢となるでしょう。
重要なのは、顧客の購買意欲が高まっているタイミングを逃さず、購入を妨げる要因を極力排除し、購入完了までスムーズに誘導できるシステムを構築することです。
さらに、購入ボタンのデザイン(大きさ、配置、色など)を最適化することも、CVR向上に繋がる有効な施策となり得ます。
15.ECサイトのページの客単価を増やすには?

ECサイトにおいて、顧客に一度の購入でより多くの商品を購入してもらうための仕組みや、高単価の商品を選んでもらうためのシステムを構築することも、工夫次第で実現可能です。
その具体的な方法としては、以下のようなものが挙げられます。
- 高単価な商品を積極的にサイトに導入する
- 商品一覧ページで高単価順に商品を閲覧できる仕組みを構築する
- セット購入を促す提案を表示する
- おすすめ商品の提案を表示する
- 「他のお客様はこのような商品も見ています」といった情報を表示する
- 一定金額以上の購入で送料無料となる特典を提供する
- ポイント制度を導入する
- ブランド別に商品を選べるようにする
- 商品ジャンル別に閲覧できるようにする
これらの施策を通じて、顧客が商品を購入する際の利便性を高める様々な仕組みをECサイト内に構築することで、ECサイト全体の平均購入単価の向上を図ることが可能です。
16.KPI・KGIの目標を達成した後のアクション

KPIを設定しただけでは、残念ながら自動的に目標が達成されるわけではありません。設定後の継続的なモニタリングと、状況に応じた柔軟な対応が不可欠です。
例えば、ECサイトの売上を向上させるというKGIを設定し、そのKPIとして「新規顧客獲得数」と「顧客単価」を設定したとしましょう。この場合、設定したKPIの達成状況を定期的に確認し、必要に応じて施策を修正していく必要があります。
具体的には、以下の手順でモニタリングと改善を進めます。
- KPIの数値化と可視化: まず、設定した「新規顧客獲得数」や「顧客単価」といったKPIを、日別、週別、月別などの単位で数値化し、グラフやダッシュボードなどで視覚的に把握できる環境を構築します。これにより、目標に対する進捗状況が一目で分かります。
- 数値の継続的な追跡: これらの数値を、設定した目標値と比較しながら、定期的に追跡していきます。例えば、「今週の新規顧客獲得数は目標に達しているか」「顧客単価は先月と比較してどう変化しているか」といった点を、継続的に確認します。
- 目標値からの乖離分析と原因特定: もし、KPIの数値が目標値を下回っている場合は、その原因を詳細に分析します。例えば、「新規顧客獲得数が目標に達していない」という場合、広告の効果が低いのか、サイトへの流入が少ないのか、あるいはサイトの使い勝手に問題があるのか、といった具体的な要因を特定します。
- 改善策の立案と実行: 原因が特定できたら、それに対する具体的な改善策を立案し、実行します。例えば、広告の効果が低いのであれば、広告のクリエイティブを変更したり、ターゲット層を見直したりといった施策が考えられます。サイトへの流入が少ないのであれば、SEO対策を強化したり、SNSでの情報発信を増やしたりといった施策が有効かもしれません。
- 効果測定とさらなる改善: 改善策を実行した後も、その効果を定期的に測定し、必要に応じてさらなる改善を行います。例えば、広告のクリエイティブを変更した結果、新規顧客獲得数がどの程度増加したのかを検証し、さらなる改善点を探します。
モニタリングの頻度は、扱うKPIの種類や、事業の状況によって異なります。
例えば、日々の売上やアクセス数など、変動の大きいKPIは、毎日モニタリングすることが望ましい場合もあります。一方、顧客の解約率など、比較的変動の少ないKPIは、週次や月次でのモニタリングでも十分な場合もあります。
重要なのは、KPIを定期的に確認し、状況に応じて柔軟に対応していくことで、最終目標であるKGIの達成へと繋げていくことです。
17.KPIを達成するために必要な確認事項

KPI達成に向けて、具体的にどのような指標をモニタリングしていく必要があるのでしょうか。
大きく分類すると、以下の3つのカテゴリーに分けられます。
- Google アナリティクス関連
- メール・SNS関連
- ECサイト内部関連
それでは、各カテゴリーについて順に説明いたします。
17-1.Googleアナリティクス関連
KPI達成のために、Google アナリティクスは非常に重要な指標群となります。
Google アナリティクスとは、Googleが無料で提供しているアクセス解析ツールであり、ECサイトを多角的に分析するための強力なツールです。
以下に、Google アナリティクスで取得できる主要な指標について、具体的な例を交えながら、説明いたします。
新規ユーザー数とリピーター率:初めてのお客様と、常連さんの割合
新規ユーザー数とは、あなたのECサイトに初めてアクセスしたユーザーの数を指します。一方、リピーター率は、過去2年以内に2回以上サイトを訪れたユーザーの割合を示すものです。
例えば、新規ユーザー数が多ければ、「広告によって新規のお客様を呼び込めている」と分析できます。また、リピーター率が高ければ、「お客様にサイトや商品が気に入られている」と判断できます。どちらも、サイトを訪れたお客様の動向を把握するための重要な指標ですので、注視しておく必要があります。
平均セッション時間:お客様がサイトにいる時間
平均セッション時間とは、お客様が1回の訪問でサイトに滞在した平均時間のことを指します。
この指標を見ることで、お客様が各ページをどのくらいの時間閲覧しているのかを把握できます。平均セッション時間が短い場合は、お客様がすぐにサイトを離脱している可能性を示唆します。これは、サイトの使い勝手や情報設計に改善の余地があるかもしれないということを示唆します。逆に、平均セッション時間が長いほど、お客様がサイト内のコンテンツに興味を持ち、長く滞在している傾向にあると言えます。
直帰率:1ページだけ見て帰っちゃったお客様の割合
直帰率とは、サイトへの訪問者のうち、最初に訪れたページのみを閲覧してすぐにサイトを離脱してしまった割合を示す指標です。
直帰率が低い場合は、お客様がサイト内で他のページも閲覧していることを意味し、サイトへの関心が高いと考えられます。逆に、直帰率が高い場合は、お客様が最初に訪れたページで目的を達成できなかったか、期待した情報が得られなかったため、すぐに離脱してしまった可能性が考えられます。これは、ランディングページの改善や、サイト全体の導線設計の見直しが必要であることを示唆します。
ページビュー数:お客様が見てくれたページの数
ページビュー数とは、お客様がサイト内のページを表示した回数のことで、「PV数」または「アクセス数」とも呼ばれます。
例えば、特定の商品ページへのページビュー数が多ければ、「その商品はお客様の関心が高い」と判断できます。ただし、同一ユーザーが同じページを複数回表示した場合も、その回数分がページビュー数としてカウントされる点に注意が必要です。
トラフィックソース:お客様がどこから来たか
トラフィックソースとは、お客様がどこからあなたのECサイトにたどり着いたか、その流入経路を示すものです。
例えば、検索エンジンからの流入が多ければ、「SEO対策が効果を発揮している」と分析できます。また、SNSからの流入が増加していれば、「SNSでの情報発信が成功している」と判断できます。トラフィックソースを把握することで、どの経路からの流入が多いのか、どの経路が効果的なのかを分析し、今後の集客戦略を立てる上で役立ちます。
これらのデータを分析することで、あなたのECサイトの現状を把握し、改善点を明確にすることができます。効果的な対策を講じるために、Google アナリティクスを積極的に活用することが重要です。
17-2.メール・SNS関連
自社ECサイトへの集客手段として、メールやInstagram・TwitterなどのSNS関連も重要な営業手段となります。これらのツールにも、ECサイト運営において注視すべきいくつかの指標が存在しますので、以下に紹介します。
メルマガ購読者数
メルマガ購読者数は、文字通り、定期的に送信するメールマガジンの購読者数を表す指標です。
メルマガ購読者が多いほど、より多くの顧客に対して、新商品情報やキャンペーン情報などを周知することが可能です。
購読数増加率
購読数増加率は、ある一定の期間において、メルマガ購読者がどれだけ増加したのかを表す指標です。
この購読数増加率が著しく向上した際には、トレンドの波に乗っている可能性が出てきます。例えば、特定のキャンペーンやイベントの告知が、新規購読者の増加に大きく貢献しているかもしれません。そのため、なぜ購読数が増加したのか、その要因を詳細に分析することが重要になります。
メール開封率
メール開封率は、送信したメールマガジンが、受信者によってどれだけ開封されているのかを表す割合です。
この数値が低い場合には、送信したメールマガジンが顧客に開封されていない恐れがあります。これは、メールのタイトルや件名が魅力的でない、あるいは送信時間帯が不適切である可能性を示唆します。そのため、メール開封率が低い場合は、これらの要素を見直し、改善策を検討する必要があります。
クリック率
クリック率は、メールマガジン内に記載したリンクが、受信者によってどれだけクリックされているのかを表す指標です。
この指標が低い場合には、メールマガジン内のリンクが顧客の興味を引けていないことを意味します。例えば、キャンペーンページへのリンクのクリック率が低い場合、キャンペーン内容やリンクの配置などに問題があるかもしれません。そのため、内容の変更や、より魅力的なリンクの作成などを検討する必要があります。
メルマガ購読の中止者数
メルマガ購読の中止者数は、文字通り、メールマガジンの購読を中止した人数を表す指標です。
万が一、メルマガ購読の中止者数が大幅に増加した際には、その要因を詳細に分析することが重要です。例えば、メールマガジンの内容が顧客のニーズと合致していない、あるいは配信頻度が高すぎるなどの原因が考えられます。
SNSフォロワー数
SNSフォロワー数は、InstagramやTwitterなどのSNSアカウントをフォローしているユーザーの数を表します。
SNSフォロワーを増やすためには、顧客にとって共感や利便性のある情報発信が重要です。例えば、商品の使い方を紹介する動画や、セール情報などを定期的に投稿することが効果的です。また、定期的なSNS発信や、キャンペーンなどの宣伝も、新規フォロワー獲得のために不可欠です。
17-3.ECサイト内部関連
承知いたしました。ECサイト内部関連の指標について、丁寧な言葉遣いで、説明的な口調を心がけ、文末は「です」「ます」で統一し、具体的な例を適宜追加する形で書き換えます。
次に、ECサイト内部関連で、ECサイトの運営において必須不可欠な指標を紹介します。
これらの指標は、Google アナリティクスと同様に、ECサイト内部の状況を直接的に示すものです。そのため、これらの指標をしっかりと理解することが、ECサイトの業績を把握し、改善策を検討する上で非常に重要となります。
売上総利益
売上総利益とは、ECサイトにおける総売上額から、売上原価を差し引いた金額です。
ここで注意すべき点は、売上原価は、売上が確定した商品にかかったコストのみを対象としているという点です。つまり、まだ売上が確定していない商品にかかったコストは、売上総利益の計算には含まれません。例えば、今月売れた商品の仕入れ費用や、それらの商品を梱包・発送するためにかかった費用などが、売上原価に含まれます。
トランザクション数
トランザクション数とは、ECサイトにおける全体的な取引の件数を表す指標です。
この指標の数値が大きいほど、ECサイト内で多くの取引が行われていることを意味します。また、CVR(コンバージョン率:商品購入率)を算出する際にも、このトランザクション数が重要なデータとして用いられます。例えば、ある期間のトランザクション数と、その期間のサイト訪問者数から、どれくらいの割合で訪問者が商品を購入したのかを把握できます。
カート放棄率
カート放棄率とは、顧客が商品をカートに入れたものの、最終的な購入手続きを完了せずにサイトから離脱してしまった割合を表す指標です。
この指標の数値が大きくなれば、サイト内での購入導線に問題がある可能性があります。例えば、決済ページへの遷移が分かりにくい、あるいは決済方法が少ないといった要因が考えられます。そのため、カート放棄率が高い場合は、これらの点を分析し、改善策を検討する必要があります。
新規orリピート・ユーザー比率
新規orリピート・ユーザー比率とは、ECサイトを訪れるユーザーのうち、新規ユーザーとリピートユーザーの割合を表す指標です。
新規ユーザーの割合が少ない場合には、SNSやWeb広告など、新規顧客を獲得するための施策を強化する必要があります。例えば、SNSでより魅力的なコンテンツを発信したり、Web広告のターゲット設定を見直したりすることが考えられます。一方、リピートユーザーの割合が少ない場合には、商品購入後のフォローアップや、顧客ロイヤリティを高めるための施策(例:ポイント制度の導入、会員限定クーポンの発行など)を検討する必要があります。
COGS(売上原価)
COGS(Cost of Goods Sold:売上原価)とは、商品を販売するまでに要した総費用を指します。
これは、商品を仕入れた際の原価だけでなく、その商品を販売するためにかかった人件費、広告費、サイト運営費用など、あらゆる費用を含めた指標です。ただし、売れ残った商品に関する費用は、COGSには含みません。例えば、今月販売した商品の仕入れ値、その商品の梱包・発送にかかった費用、その商品を宣伝するためにかけた広告費などが、COGSに含まれます。
18.ECサイトにおけるKPI設定をする際の具体例
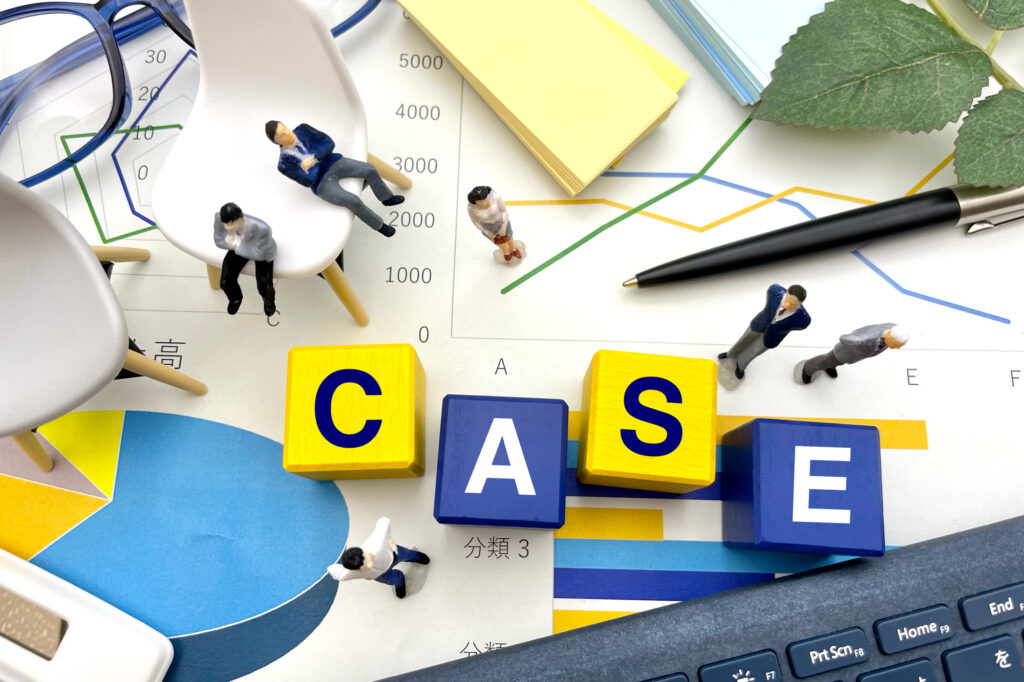
KPIの具体的な例として、あなたが現在、健康食品のECサイトを運営している状況を想定してみましょう。
現在のあなたのECサイトの実績は、以下の通りであるとします。
- 月商:1,000万円
- 訪問者数:100,000人
- 購入割合(CVR):1%
- 平均購入単価:1万円
ここで、あなたが事業拡大を目指し、3ヶ月後のKGI(重要目標達成指標)として、月商2,000万円を掲げたとします。
この目標を達成するためには、「訪問者数」「購入割合(CVR)」「平均購入単価」のいずれか、または全ての要素を改善する必要があります。そのため、「訪問者数」「購入割合(CVR)」「平均購入単価」を定量化し、具体的な施策を立案・実行する以外に方法はありません。
KPIツリーを作成し、各要素に目標数値を設定することで、目標達成までのプロセスや必要な施策を可視化することができます。KPIを定量化することで、目標到達までに具体的に何をすべきなのか、その仮説を立て、実行に移すことが可能となるのです。
19.ECサイトの成長に向けた効果検証

KPIやKGIを設定したからといって、それだけでECサイトが自動的に成長するわけではありません。重要なのは、設定したKPIに紐づく具体的な施策を実行し、その結果を検証していくことです。そうすることで、各要素に設定した目標数値に近づいていくのです。
ここで、特に重要となるのが「検証」というプロセスです。実際に施策を実行するだけでなく、その実行結果を振り返り、分析することが不可欠です。ECサイトを効率的に成長させていくためにも、PDCAサイクルなどのフレームワークを活用し、定期的に振り返りと分析を行うことが推奨されます。
20.ECサイトの成長に向けたGoogleアナリティクスの活用方法

ECサイトを運営する上で、定期的にモニタリングを行うことは非常に重要です。PDCAサイクルを効果的に回していくためにも、どのような指標をモニタリングする必要があるのかを、ここではGoogleアナリティクスのデータを参照しながら解説します。
新規ユーザーとリピーター率
最初にモニタリングしておきたい指標は、新規ユーザーとリピーター率です。新規ユーザーとリピーターの比率がどの程度であるかを、必ず確認しておく必要があります。新規ユーザー数の伸びも重要ではありますが、安定してECサイトを運営していくためには、リピーター率を向上させることに重点を置くことが重要です。
平均セッション継続時間
ECサイト運営において特に注目したい指標の一つが、平均セッション継続時間です。これは、ユーザーがサイトにどれくらいの時間滞在したかを示す指標となります。平均セッション継続時間が短い場合は、「コンテンツに魅力がない」「商品が上手く訴求できていない」などの原因が考えられるため、早急な対策を講じる必要があります。
直帰率
直帰率は、平均セッション継続時間と並んで、コンテンツの質を評価するための重要な指標となります。直帰率とは、サイトに訪れたユーザーが、他のページに遷移することなく、最初に訪れたページのみを閲覧してサイトを離脱してしまった割合を示すものです。直帰率は、できるだけ低い数値を維持することが望ましいです。
セッションあたりの平均ページビュー
セッションあたりの平均ページビューとは、ユーザーが1回の訪問でサイト内のページを何ページ閲覧したかを示す指標です。サイト内回遊率などとも呼ばれています。この指標の数値は、多い方が一般的には良いとされますが、注意すべき点もあります。多くのページを閲覧している場合でも、それがユーザーの興味関心に基づく積極的な行動であるとは限りません。例えば、サイトのユーザビリティが悪く、目的のページにたどり着くために複数のページを閲覧している場合などは、改善が必要となります。
21.ECサイトにおける仮説を実行した後の分析

仮説を立てて施策を実行した後、その結果を分析することは、ECサイト運営において非常に重要なプロセスですが、同時に、多くの労力を要する作業でもあります。なぜなら、様々な数値を追跡する必要があり、場合によっては、複数の分析ツールを横断的に使用して分析を行う必要が出てくるからです。
そこで、分析作業を効率化する上で便利なツールとなるのが、「CRMツール」(Customer Relationship Management:顧客関係管理ツール)です。CRMツールは、顧客に関する分析はもちろんのこと、ECサイト運営に必要な様々なデータを一元的に取得することができるため、より詳細な分析を、1つのツールで完結させることが可能になります。
ECサイトに特化しているCRMツールも存在します。これらのツールは、ECサイト運営に特化した機能を提供しているため、導入を検討してみるのも有効な選択肢と言えるでしょう。
22.ECサイトにおける成功した事例の紹介
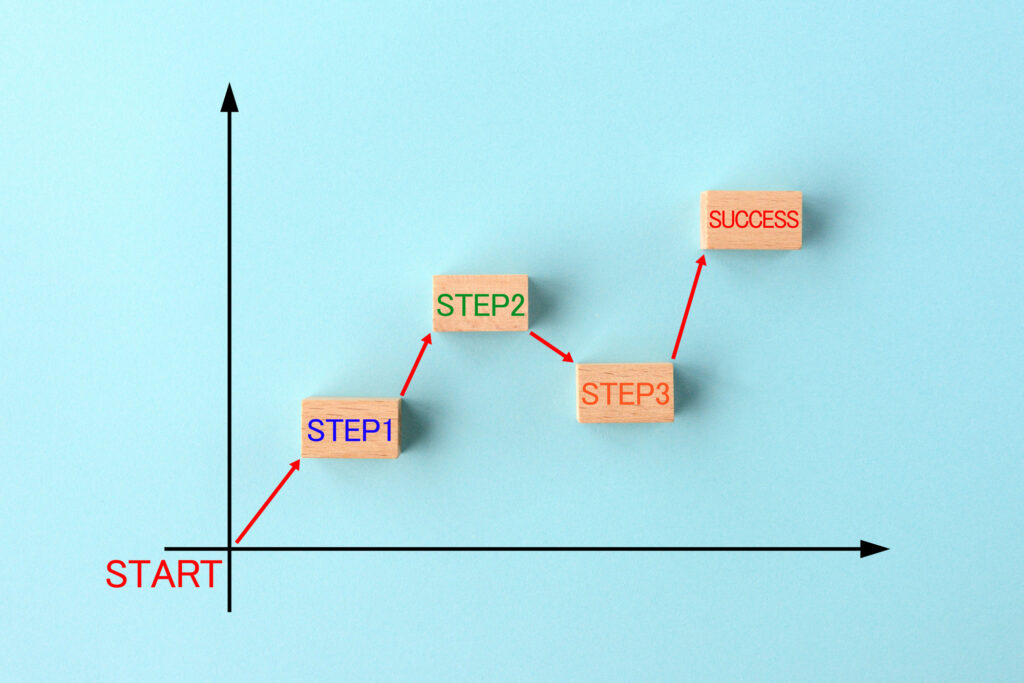
Cサイト運営において、成功を収めるためには、以下の点が特に重要となります。
- 自社ECサイトを、単なる販売チャネルではなく、情報発信基地としての役割も持たせること。 お客様にとって有益な情報を提供することで、サイトへの訪問頻度を高め、購買意欲を醸成することが重要です。例えば、商品に関する詳細な情報だけでなく、関連するお役立ち情報や、お客様の声などを掲載することで、サイトの価値を高めることができます。
- お客様が購入を検討する上で抱く可能性のある疑問や不安を、事前に解消すること。 商品の品質、安全性、配送方法、返品ポリシーなどについて、明確かつ分かりやすく説明することで、お客様は安心して購入を決定できます。例えば、よくある質問コーナー(FAQ)を充実させたり、チャットサポートを導入したりすることが有効です。
- お客様が実際に商品を使用する場面を具体的にイメージできるような、魅力的なサイト設計を行うこと。 商品の特徴や魅力を最大限に伝えるために、高品質な商品画像や動画を使用したり、使用シーンを想起させるようなストーリー性のあるコンテンツを作成したりすることが重要です。例えば、アパレル商品であれば、様々なコーディネート例を提示したり、着用感を詳しく解説したりすることが効果的です。
- お客様が商品を購入するまでの心理的なプロセスを想定し、購買意欲を高めるための導線を設計すること。 お客様がサイトを訪れてから商品を購入するまでの流れを、ステップごとに分析し、各ステップにおいてお客様の購買意欲を高めるための施策を検討します。例えば、商品ページへのアクセスを促すためのキャンペーンを実施したり、カートに入れた商品を後で購入できるように保存する機能を提供したりすることが有効です。
- ECサイト全体の改善効果を最大化するために、改善のインパクトが大きい箇所から優先的に取り組むこと。 アクセス解析データなどを参考に、サイト内で最も改善の余地が大きい箇所を特定し、そこから優先的に改善を進めることで、効率的に成果を上げることができます。例えば、直帰率の高いページや、離脱率の高いページを特定し、それらのページを重点的に改善することが効果的です。
実際に、上記の項目を総合的に改善し、ECサイト運営で大きな成功を収めている企業として、「セブンイレブン」や「Abercrombie & Fitch」などの事例が挙げられます。
22-1.セブンイレブン
セブンイレブンの強みの一つは、全国に21,733(2025年3月末現在)という、日本最大の店舗網を誇るコンビニエンスストアである点です。
この圧倒的な店舗網を活かし、セブンイレブンは、コンビニエンスストアで取り扱う商品をインターネット上で販売するECサービス「ネットコンビニ」を全国に展開しています。
「ネットコンビニ」では、顧客がスマートフォンを使って商品を注文すると、最短2時間で商品が自宅に届くという、迅速な配送サービスを提供しています。注文受付時間は午前7時から午後5時までで、注文最低金額は1,000円、送料は216円です。ただし、購入金額が3,000円以上の場合、送料は無料となります(送料はセブン-イレブン・ジャパンが負担)。
このような「ネットコンビニ」の取り組みを通じて、セブンイレブンは、顧客一人ひとりのニーズに合わせた、きめ細やかなパーソナル販売を強化しています。
22-2.Abercrombie & Fitch
世界的にも知名度の高いアパレルブランドであるAbercrombie & Fitchですが、同社のECサイトでは、以下のような取り組みが行われています。
Abercrombie & Fitchのスマートフォンサイトでは、オンラインショッピングが可能であり、商品一覧画面からカラーバリエーションを容易に選択できる機能が提供されています。また、実際に商品を着用した際のイメージを伝えることに重点が置かれており、様々な着用写真や動画が掲載されています。
このように、ECサイト運営を成功させるためには、顧客の視点に立ち、顧客にとって使いやすく、魅力的なサイト設計を行うことが重要であることが分かります。
23.まとめ
ECサイト運営において、KPI(重要業績評価指標)とKGI(重要目標達成指標)の設定は、目標達成に向けた施策を明確にし、効果測定を行う上で非常に重要です。KPIはKGIを達成するための中間目標として設定され、売上、アクセス数、CVR(転換率)、客単価などが主要な項目となります。
KPIの設定においては、KGIとの連動、定量化、期間設定が重要であり、SMARTフレームワークを活用することで、より効果的なKPI設定が可能となります。また、KSF(重要成功要因)を検討することも、KGI達成に不可欠な要素です。
ECサイトの成長を促進するためには、アクセス数、CVR、客単価、回遊率、リピート率、離脱率、顧客獲得単価、売上高、LTV(顧客生涯価値)などのKPIを適切に管理し、マーケティング活動においては、滞在時間、トラフィックソース、メルマガ購読者数、メール開封率、クリック数などの指標を分析することが重要となります。
在庫管理においては、過剰在庫、在庫欠品率、在庫保管コストなどのKPIを最適化することで、効率的な運営を実現できます。
KPIツリーは、KGIを頂点にKPIを構造化したもので、目標達成までの道筋を可視化し、課題発見や情報共有、迅速な施策実行を促進する効果があります。
施策実行後は、PDCAサイクルに基づいた効果検証が不可欠であり、GoogleアナリティクスやCRMツールなどの分析ツールを有効活用することが推奨されます。
ECサイト運営の成功事例として、情報発信、顧客の不安解消、商品イメージの喚起、購買導線設計、改善の優先順位付けなどが挙げられ、セブンイレブンやAbercrombie & Fitchなどの企業が、これらの要素を効果的に取り入れていました。
ぜひ今回の記事を参考に、KPIを正しく設定し、ECサイトでの売上を伸ばしていっていただければと思います。
ECサイトへの出店、運用に関してのご質問やご相談などございましたら、ECにおける総合的な売上向上サービスを展開しております弊社にお気軽にお問い合わせください。

株式会社Proteinum 代表取締役
プロテーナムでは、楽天、amazon、自社EC、Yahoo!ショッピングを中心に、データに基づく圧倒的な成果にこだわった支援を行っている。ナショナルブランドを中心に累計1,000社以上の支援と年間広告費10億円以上の運用実績を持ち、独自のEC運用支援システム「ECPRO」も提供している。