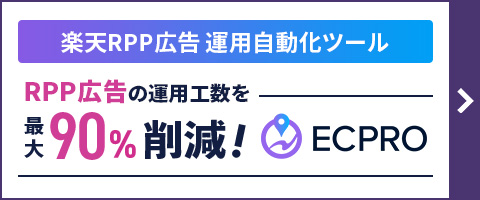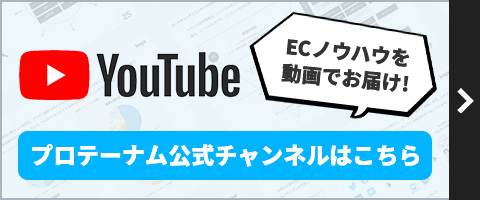今話題のUGCとは何か?注目される理由とマーケティングで活用する際のポイントを解説!

本記事を閲覧頂きありがとうございます。 我々はECにおける総合的な売上向上サービスを展開しています。 楽天、Amazon、Yahoo!ショッピングの大手ECモールや自社サイトのご支援実績のもと、EC売上向上のノウハウをお届けします。
「SNSで話題沸騰!」「購入者のリアルな声が決め手!」近年、このような言葉をECサイトや広告で見かける機会が格段に増えました。これらのキーワードの背後には、「UGC(User Generated Content)」と呼ばれる、ユーザー自身が創造し、発信するコンテンツの存在があります。
企業が発信する一方的な情報ではなく、実際に商品やサービスを利用した個人の体験に基づいたUGCは、消費者の購買行動に大きな影響を与える力を持っています。特にECマーケティングにおいては、集客、顧客エンゲージメント向上、そして売上増加に不可欠な要素として、その重要性がますます高まっています。
本記事では、UGCの基本的な概念から、なぜ現代においてこれほど注目を集めているのか、そしてECマーケティングでどのように効果的に活用できるのかを徹底的に解説します。ECサイトの運営者の方、マーケティング担当者の方で、UGCの可能性を探り、具体的な活用方法を学びたいとお考えの方は、ぜひ最後までお読みください。
Contents
1.UGCの概要
まず、UGC(User Generated Content)とは具体的にどのようなコンテンツを指すのか、そして混同されやすいCGM(Consumer Generated Media)やIGU(Influencer Generated Content)といった類似の概念との違いを明確にしていきましょう。
1-1.UGCとは?
UGC(User Generated Content)とは、一般ユーザーによって制作・発信されたコンテンツの総称です。企業が作成した広告や公式コンテンツとは異なり、個人の視点や体験に基づいて生み出される点が大きな特徴です。
その形態は非常に多様であり、テキスト、画像、動画、音声など、様々な形式で存在します。
①テキストコンテンツ
・レビュー、口コミ:ECサイトの商品レビュー、グルメサイトの評価、旅行サイトの体験談など、商品やサービスに関する評価や感想。
・SNS投稿(テキスト):Xのつぶやき、Facebookの近況アップデート、Instagramのキャプションなど、SNS上でのテキストによるコメントや意見。
・ブログ記事:個人のブログで書かれた商品レビュー、体験談、ハウツー記事など。
・Q&Aサイトの回答:Yahoo!知恵袋やQuoraなどのQ&Aサイトにおける、ユーザーからの質問に対する回答。
・フォーラム、掲示板の投稿:特定のテーマに関するオンラインコミュニティや掲示板での意見交換や情報提供。
②画像・動画コンテンツ
・SNS投稿(画像・動画):Instagramの写真やストーリーズ、TikTokの動画、YouTubeのレビュー動画、商品の使用風景を撮影した写真など。
・ECサイトへの投稿画像:購入者が商品を実際に使用している写真や、商品の魅力を伝える写真。
・ライブ配信:Instagram LiveやYouTube Liveなどで行われる、商品紹介やレビューなどのライブ配信。
③音声コンテンツ
・ポッドキャスト:個人のパーソナリティが配信する、商品レビューや体験談などの音声コンテンツ。
・音声SNSでの発言:ClubhouseやVoicyなど、音声SNSプラットフォームでの意見交換や情報発信。
これらのUGCは、SNS、ブログ、レビューサイト、ECサイトの商品レビュー欄、動画共有プラットフォーム、音声SNSなど、多岐にわたるオンラインプラットフォームを通じて発信され、他のユーザーの目に触れることになります。UGCの力は、そのリアルさと共感性にあり、企業が発信する情報よりも信頼性が高いと認識される傾向が強いと言えます。
1-2.CGMとの違い
UGCと似た言葉にCGM(Consumer Generated Media)があります。CGMは、消費者自身が情報を発信・共有するメディアの形態を指します。CGMは、消費者が自ら情報を発信・共有する「場」や「メディア」の形態を指します。具体的には、ブログサービス、SNSプラットフォーム(Facebook、X、Instagramなど)、掲示板、Q&Aサイト、動画共有サイト(YouTube、TikTokなど)、クックパッド、知恵袋などが該当します。
UGCは、CGMという大きな枠組みの中で、ユーザーによって「生成されたコンテンツそのもの」を指すのに対し、CGMは「ユーザーがコンテンツを生成・共有するプラットフォームやメディア(場所)」を指すという違いがあります。
CGMは、ユーザーが情報発信やコミュニケーションを行うためのプラットフォームであり、UGCはそのプラットフォーム上で生まれる具体的な成果物と言えるでしょう。企業がCGMを活用する際には、そこで生まれるUGCをどのように活用していくかが重要なポイントとなります。
1-3.IGUとの違い
IGU(Influencer Generated Content)は、インフルエンサーと呼ばれる、特定の分野において強い影響力を持つ個人が作成したコンテンツのことです。
UGCは、一般のユーザー全体によって自発的に生成されるコンテンツであるのに対し、IGUは、特定のインフルエンサーという個人によって作成される点が異なります。また、IGUは、企業からの依頼に基づいて商品やサービスを紹介するプロモーションの側面を持つ場合が多いのも特徴です。
IGUは、その影響力の大きさから、特定のターゲット層へのリーチや購買意欲の喚起に高い効果が期待できます。しかし、企業からの依頼によるPR投稿である場合、純粋なユーザーの声としての信頼性はUGCと比較して低いと認識されることもあります。
ただし、インフルエンサーが企業からの依頼ではなく、自発的に商品やサービスについて言及するコンテンツは、広義のUGCに含まれると考えることもできます。近年では、企業がインフルエンサーに商品体験を提供し、その体験に基づいたリアルな感想をUGCとして発信してもらうマーケティング手法も注目されています。この場合、IGUは信頼性の高いUGCとして機能する可能性を秘めています。
2.UGCが注目されるようになった理由
近年、企業のマーケティング戦略において、UGCが無視できない存在感を放つようになっています。その背景には、社会全体の変化や消費者の行動変容、そしてEC市場の特性など、様々な要因が複雑に絡み合っています。一般的な観点とECマーケティングにおける観点の両面から、UGCが注目を集めるようになった理由を深掘りしていきましょう。
2-1.一般的な観点
①消費者の情報収集行動の変化
インターネットとスマートフォンの普及により、消費者は商品やサービスを購入する前に、オンラインで徹底的に情報を収集するようになりました。従来のトップダウン型の情報伝達ではなく、水平方向の、つまり他の消費者からの情報を重視する傾向が顕著になっています。企業が発信する広告や公式情報だけでなく、実際に商品を利用したユーザーのリアルな声や評価を参考に、購入の意思決定を行うことが一般的になっています。
キャプテラの「2024年オンライン消費者実態調査」では、オンラインで新商品やサービスを購入する際に、約7割はインターネット検索エンジンを利用していることが分かります。
参考:キャプテラ2024「2024年オンライン消費者実態調査」
https://www.capterra.jp/blog/6469/sns-online-consumers-searching-products
②SNSの普及と共感の重視
X、Instagram、Facebook、TikTokといったSNSプラットフォームは、現代社会において人々の情報収集、コミュニケーション、自己表現の主要な場となっています。これらのプラットフォームでは、「いいね」やコメント、シェアといった機能を通じて、ユーザー同士の共感や繋がりが重視されます。他のユーザーの投稿、特にポジティブな体験談や共感を呼ぶコンテンツは、見た人の感情に強く訴えかけ、購買意欲を刺激する力を持っています。
キャプテラの「2024年オンライン消費者実態調査」では、オンラインで新商品やサービスを購入する際、28%がソーシャルメディアを活用しているという結果がでています。
参考:キャプテラ2024「2024年オンライン消費者実態調査」
https://www.capterra.jp/blog/6469/sns-online-consumers-searching-products
③情報過多と広告への不信感
インターネット上には日々膨大な量の情報が溢れかえっており、消費者はその情報洪水の中で、何が真実で信頼できる情報なのかを見極めることに苦労しています。特に、企業が一方的に発信する広告に対しては、誇張された表現や都合の良い情報ばかりが伝えられているのではないかという不信感が根強く存在します。一方、UGCは、企業と利害関係のない第三者である一般ユーザーによって発信されるため、より客観的で信頼性が高い情報として認識されやすい傾向があります。
④個性を重視する消費者の増加
大量生産・大量消費の時代から、個人の価値観やライフスタイルを重視する消費者が増えています。UGCは、多様なユーザーによるリアルな体験談やレビューを通じて、商品の個性や魅力をより具体的に伝えることができます。
⑤体験価値重視へのシフト
モノの所有だけでなく、商品やサービスを通じて得られる体験そのものに価値を見出す消費者が増えています。UGCは、実際に商品やサービスを利用したユーザーの体験談をリアルに伝えることができるため、購入を検討しているユーザーにとって、その商品やサービスが自身のライフスタイルにどのような価値をもたらしてくれるのかを具体的にイメージする手助けとなります。
2-2.ECマーケティングにおける観点
①顧客エンゲージメントの向上
ECサイトにおいては、一度購入して終わりではなく、顧客との長期的な関係性を構築し、リピーターを育成することが重要です。UGCを積極的に活用し、投稿してくれたユーザーとコミュニケーションを取ることで、顧客ロイヤリティを高め、長期的な関係性を築きやすくなります。
②ユーザーの不安解消
商品購入を検討しているユーザーにとって、実際に購入した人のレビューや使用感は非常に参考になります。UGCをECサイト上に掲載することで、購入への不安を解消することができます。
③コストを抑えてた自社コンテンツの充実
SEO対策という観点で、企業が新たなコンテンツを発信するのにはコストがかかります。UGCを活用することができれば、企業が一からコンテンツを作るよりも圧倒的に低コストでサイトの内容を充実させることができます。
④商品開発や改善へのヒント
ユーザーからの率直な意見や感想が詰まったUGCは、企業にとって非常に貴重なフィードバックとなります。商品の使いやすさ、改善点、新たなニーズなど、UGCを分析することで、商品開発やサービス改善のヒントを得ることができます。顧客の視点を取り入れることで、より顧客満足度の高い商品やサービスを提供できるようになります。
⑤競争の激化と差別化の必要性
EC市場は競争が激しく、多くのECサイトが類似の商品やサービスを提供しています。そのような状況下で、自社のECサイトを差別化し、顧客に選ばれるためには、商品の魅力だけでなく、顧客体験全体を向上させる必要があります。UGCは、商品のリアルな情報を伝えるだけでなく、顧客とのコミュニケーションを促進し、エンゲージメントを高めることで、独自のブランド体験を創出するのに貢献します。
3.ECでUGCを活用するメリット
ECサイトでUGCを活用することには、以下のような具体的なメリットがあります。
3-1.信頼性の向上
今までの広告は、製品・サービスの良い面にばかりフォーカスされる傾向にあります。それは、消費者側からすると欠点が見えにくいことに加え、鬱陶しさを感じてしまうこともあります。その点UGCは、消費者の目線で商品が紹介されているため、良い面ばかりを紹介する企業の広告よりも信頼されやすい傾向にあります。
上記の理由から、ユーザーは、企業が発信する情報よりも同じ消費者である他のユーザーの意見を信頼する傾向があります。商品レビューやSNSでの口コミは、購入を検討しているユーザーにとって、商品の品質や使用感を判断する上で非常に重要な情報源となります。UGCが豊富に掲載されているECサイトは、ユーザーからの信頼を得やすく、安心して買い物をしてもらえる環境を提供できます。
キャプテラの「2024年オンライン消費者実態調査」では、ネットショッピングにSNSを利用する理由として、興味のある商品探しが最も主要な目的であり (68%)、次いで商品レビューの検索 (55%)という結果がでております。商品を購入する際に、ユーザーは、同じ目線に立つユーザーの口コミをどれだけ重要視しているかが分かります。
参考:キャプテラ2024「2024年オンライン消費者実態調査」
https://www.capterra.jp/blog/6469/sns-online-consumers-searching-products
3-2.顧客体験の向上
UGCは、商品の抽象的な情報だけでなく、具体的な利用シーンやメリットを伝えることで、ユーザーの購買意欲を効果的に高めます。例えば、アパレルECサイトであれば、実際にユーザーが商品を着用している写真やコーディネート例は、他のユーザーにとって非常に参考になり、自分自身が着用した際のイメージを具体的に想像する手助けとなります。また、商品のメリットだけでなく、デメリットや注意点なども正直に語られたレビューは、ユーザーの納得感を高め、購入後のギャップを減らす効果も期待できます。
3-3.自然な形での認知度拡大と新規顧客の獲得
ユーザーが自発的にSNSなどのプラットフォームで商品やブランドについて言及することで、その投稿を見た他のユーザーへの認知が自然に広がります。特に、共感や話題性を呼ぶUGCは、口コミとして拡散されやすく、広告に頼らずともブランドの認知度を向上させ、新たな顧客を獲得する可能性を秘めています。ユーザーが友人に商品を勧めるような形で情報が広がるため、高い信頼性と訴求力を持つことが期待できます。
3-4.SEO(検索エンジン最適化)効果の向上
UGCには、ユーザーが商品を探す際に使用する可能性のあるキーワード(商品名、関連語句、悩みに関する言葉など)が自然に含まれることが多く、ECサイトのコンテンツを充実させる効果があります。特に、レビューコンテンツは、検索エンジンが重視する新鮮で多様なコンテンツとして評価されやすく、ECサイト全体の検索順位向上に貢献する可能性があります。また、UGCを通じてロングテールキーワードでの流入も期待できます。
3-5.運営コストの効率化と顧客サポートの軽減
ユーザーが自発的に商品の疑問に答えたり、使用方法を共有したりするUGCは、ECサイトのコンテンツ不足を補い、カスタマーサポートへの問い合わせを減らす効果も期待できます。特に、よくある質問とその回答がUGCとして蓄積されることで、運営側の負担を軽減することができます。また、レビューコンテンツは、商品に関する詳細な情報を提供することで、購入前の不安を解消し、結果的に返品率の低下にも繋がる可能性があります。
4.ECマーケティングにおけるUGCの活用方法
UGCをマーケティングに活用する上で重要なのは、戦略的な流れを構築することです。
以下、3つのステップを循環させることで、UGCを継続的に活用し、マーケティング効果を最大化することができます。
4-1.UGCの創出
顧客にUGCを投稿してもらうためには、インセンティブ設計が重要です。レビュー投稿へのポイント付与やSNSキャンペーンの実施は、顧客の参加意欲を高めます。また、レビューフォームの簡便化やSNS連携の強化など、顧客が容易にコンテンツを発信できる環境を整えることも大切です。投稿してほしい内容や注意点を明確なガイドラインとして提示しましょう。
4-2.UGCの収集
ECサイトのレビュー機能やSNSモニタリングツールを活用し、多様なUGCを効率的に集めます。
場合によっては膨大なデータになることもあるため、収集をする際は、事前に目的を明確にしておくことをおすすめします。
4-3.UGCの分析
収集したUGCを分析し、顧客の声やトレンドを把握することで、商品開発やプロモーション改善の貴重な示唆を得ます。
5.ECマーケティングでUGCを活用する際のポイントと注意点
ECマーケティングでUGCを効果的に活用するためには、いくつかのポイントと注意点があります。
5-1.ECマーケティングでUGCを活用する際のポイント
UGCをマーケティングに活用する際のポイントを「ULSSAS」というフレームワークを軸に解説いたします。
「ULSSAS(ウルサス)」とは、ソーシャルメディアマーケティングにおいて成果を出すための重要な要素をまとめたフレームワークであり、以下の6つの要素の頭文字を取ったものです。
U・・・UGC(User Generated Content):ユーザーによって生成されたコンテンツ。レビュー、口コミ、SNS投稿を行う。
L・・・:Like(いいね):UGCを見たユーザーが投稿にいいねやリツイートをする。エンゲージメントが高くなるとリーチが伸び、より多くの人の目に触れるようになる。
S・・・Search1(SNS検索):いいねがついたUGCを見たユーザーが、商品について気になり始める。SNS上で検索をして情報収集する。
S・・・Search2(Google/Yahoo!検索):商品を買える最寄りの店舗を知りたいと思い、検索エンジンで指名検索をする。
A・・・Action(購買):店舗に足を運び、商品を購入する。
S・・・Spread(拡散):コンテンツがユーザー間で広まること。商品の写真を撮り、それをTwitter上に投稿する。その投稿(UGC)にまたいいねがつき、ULSSASのサイクルが回り始める。
UGGのマーケティングにこの「ULSSAS」の視点を取り入れることで、より効果的なUGC活用戦略を立てることができます。
5-2.ECマーケティングでUGCを活用する際の注意点
UGCは強力なマーケティングツールである一方、活用する際にはいくつかの注意点があります。
①目的の明確化
UGCを活用する目的を明確にすることが重要です。認知度向上、顧客エンゲージメント向上、コンバージョン率向上など、目的に合わせて適切な活用方法を選択する必要があります。
②ブランイメージの維持
UGGの上質さや温かさといったブランドイメージを損なう可能性のあるUGCは慎重に取り扱う必要があります。不適切なコンテンツは、ブランド価値を毀損する恐れがあるため、監視体制を整えることが重要です。
③ガイドラインの策定
UGCの利用規約やガイドラインを明確に定め、ユーザーに安心してコンテンツを投稿してもらえる環境を整備します。著作権や肖像権、個人情報保護などにも配慮が必要です。
④ステルスマーケティングの禁止
インフルエンサーなどに依頼してUGCを作成してもらう場合、広告であることを明記する必要があります。ステルスマーケティングは、消費者の信頼を損なうだけでなく、法律に触れる可能性もあります。
ステルスマーケティング規制に違反してしまうと、都道府県や消費者庁から措置命令が下されるほか、事業者名が公表される可能性もあります。また、措置命令に従わなかった場合は、2年以下の懲役または300万円以下の罰金などが科せられます。このようなトラブルを引き起こさないためにも、UGCを活用する際はルールを明確に決めて実施するようにしましょう。
⑤ネガティブなUGCへの対応
ネガティブなレビューや意見も真摯に受け止め、改善に繋げる姿勢が重要です。必要に応じて、ユーザーに直接連絡を取り、状況を確認したり、謝罪や説明を行ったりすることも検討しましょう。
⑥炎上対策
UGGに関する不適切なUGCや炎上につながる可能性のある投稿に対しては、迅速かつ適切に対応するための体制を整えておく必要があります。
⑦効果測定と改善
UGCを活用したマーケティング施策の効果を定期的に測定し、エンゲージメント数、リーチ数、コンバージョン率などを分析し、改善を繰り返していくことが重要です。
⑧クオリティーがユーザーによって異なる
UGCはユーザーが生成するコンテンツであることを忘れてはいけません。そのため、ユーザーの技量によりコンテンツの質にばらつきが生まれてし舞う可能性があります。それを防ぐためには、ユーザーに丸投げをするのではなく、ユーザー自身が投稿したい、 レビューを書きたいという意欲を掻き立てるような商品・サービスの提供やハッシュタグキャンペーンなどのイベントの実施が必要になります。
また、投稿内容の制御が難しいため、ネガティブなコンテンツとなり、企業の信頼を失うことになる可能性があることも事実です、しかし、ネガティブな投稿内容も消費者にとっては貴重な参考意見です。上記でもご説明したように、むやみになくすのではなく、ネガティブなレビューや意見も真摯に受け止め、改善に繋げる姿勢が必要になってきます。しかし、間違った情報の発信や悪質なデマなどが見つかった場合は、できるだけ早く訂正し、正しい情報を発信していく必要があります。
6.UGC活用に役立つツール
最後にUGC活用に役立つツールを2つ紹介します。
6-1.Yotpo
株式会社ギャプライズが運営する、UGCマーケティングツールです。
レビュー、評価、Q&A、ビジュアルUGC(写真・動画)、ロイヤリティプログラムなどを一元管理できる統合プラットフォームです。特にECサイトとの連携に強く、購入後のレビュー収集を自動化する機能や、収集したUGCを商品ページやSNS広告に活用する機能が充実しています。
6-2.EmbedSocial
Embedsocial Japan株式会社が運営する、SNSに特化したUGC収集・表示ツールです。Instagram、Facebook、Xなどの投稿を収集し、ウェブサイトやデジタルサイネージなどに簡単に埋め込むことができます。手頃な価格で導入しやすく、SNS上のUGCを手軽に活用したい場合に適しています。
これらのツールは、UGCの収集、管理、活用を効率化し、マーケティング効果の最大化を支援します。自社のビジネス規模や目的に合わせて、最適なツールを選択することが重要です。
7.まとめ
UGCは、現代のECマーケティングにおいて、顧客との信頼関係を築き、売上向上を実現するための強力な武器となります。ユーザーのリアルな声は、広告よりも説得力があり、購買意欲を大きく左右します。
本記事で解説したように、UGCの活用方法は多岐に渡ります。まずは、自社のECサイトの課題や目標に合わせて、最適なUGC活用戦略を検討してみてはいかがでしょうか。
UGCを積極的に取り入れ、顧客と共に成長するECサイトを目指しましょう。

株式会社Proteinum 代表取締役